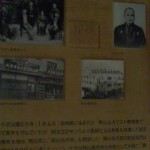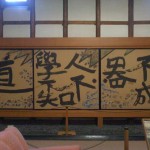カテゴリー 『 アート 』
倉敷、児島虎次郎記念館
もうすっかり秋ですね。
同時に台風シーズンでもあります。
今日は関東もあちこちで大雨警報が出ていますが、皆さんの地域は大丈夫でしょうか?
☆
☆
8月も数日で終わるという日に、所用で岡山に行ったのですが、せっかくなので倉敷にも足を伸ばしました。
☆
☆
夏の観光のピークも過ぎ、何となく「祭りの後」のようなもの悲しい感じさえ漂っていました。ビアガーデンは閉まっているし(アルコールがダメな私には関係ないですが)、観光客もまばらで、「もう夏は終わりだなあ」という空気が感じられました。
そんな中、ふと入った「児島虎次郎記念館」がよかったです。
ここも観覧者は私と、他に一人だけ。建物は明治期の紡績工場の織物倉庫なので、重い織物を天井まで積み上げたときに耐えられるよう床板の厚さが6~7センチはあろうかという重厚な建物です。現在のクラボウ(倉敷紡績)の発祥の地になります。
児島虎次郎さんの絵が素晴らしかったです。有名な大原美術館の所蔵絵画は、倉敷紡績のオーナーであり、美術館創設者の大原さんが、パリ在住の児島虎次郎の進言で収集を始めたものだそうで、当時まだパリ画壇でも注目されていなかった印象派の絵画もいち早く収集しているのは、児島の審美眼の的確さゆえだったと思われます。あの有名なエル・グレコの「受胎告知」も実物がここにあるのです。
東京の美術館などに比べると、本当にさりげなく展示されていて、そこにまた親しみを感じました。(写真を撮るのも忘れて見学していて、ほとんど写真がありません。何となく雰囲気を感じていただければ・・・)
感動したことがもう一つあります。
大原孫三郎さんは企業人であると同時に、社会貢献でも重要な仕事をしていました。友人のクリスチャンに影響を受けたそうですが、社員の健康や安全な労働管理、生活支援のための生協活動や厚生設備、社員のための保育所整備や孤児院の運営まで、企業の発展を図りつつ、社会的にも大きな貢献もしていたという事実は、写真や事実で読むだけでも胸のすく思いがしました。
今の社会を見るとき、大企業の多くが収益を一部の者の懐を潤すことのみに使い、そこで働く労働者がないがしろにされ、地域社会にも冷淡であるという事実が社会問題にすらなっています。明治期の企業人には、大原さんに限らず、社会全体を視野に入れ、人間的な目て企業を運営する視点と度量があったのです。そうした人物を生み出す社会、そうした人物を育てる教育であってほしいとつくづく思います。
結局半日を、児島虎次郎記念館と大原美術館で費やし、他の観光地は観ることもなく帰ってきてしまったのですが、それでも大満足でした。とっても幸せな半日を過ごすことができましたから…。もし、倉敷にいらっしゃたら、大原美術館はもちろん、児島虎次郎記念館にも、ぜひ足を運んでみてください(先に児島虎次郎記念館を観て、それから大原美術館に行くのがお薦めです。係の女性のアドバイスなんですが、より味わいが深まります)。
歌で涙が・・・
先日、「フタバから遠く離れて」という映画を見ました。東日本大震災で被災した福島県双葉町が埼玉県加須市に避難してからの日々を追ったドキュメンタリーです。その中の一場面に、自衛隊の音楽隊が慰問に訪れて演奏する様子が映されていました。
楽隊をバックに隊員の男性がマイクを持って歌います。曲は「寅さん」だったでしょうか(たぶん)?ついで、福島県か双葉町の歌でしょうか?曲調と歌詞から判断して(たぶん)。これら歌の場面はほんの数十秒だったのですが、耳にしたとたんに、なぜか涙がこぼれてしまったのです。
私は特に寅さんのファンでもありません。特別に双葉町に対して深い思い入れがあるわけでもありません。確かに埼玉県に避難してこられた唯一の自治体という意味では、当初より関心は持っていましたが、しかしだからといってことさら双葉町に、まして町の歌に関心があったわけでもありません。にもかかわらず、曲を聴いたとたんに、なぜかわかりませんが、涙がこぼれてしまったのです。自分でもビックリしました。なぜここで?!
何の涙なのか自分でもわかりません。おそらく、そうした言葉にできない気持ちを涙が代弁してくれたのでしょう。
直接被災したわけではない私であっても、震災以来の被災地での過酷な体験談を聞いたり、今に続く原発や放射能にまつわる情報や今後の対応などを考える中で、知らぬ間にため込んでいた緊張もあったと思います。そうした諸々の思いが含まれていたような気がします。そうしたすべてが、音楽によって一気にあふれ出てきた、そんな感じだった気がします。
音楽の持つ力というものに改めて感心しました。言葉にできない思いを表してくれる手段だということがまさに実感できました。
そして思いました。
歌える人、いいですね!
楽器の演奏できる人、素敵ですね!
どうかたくさんたくさん、私たちの周りに音楽をあふれさせてください。
機会があれば歌ってください。
演奏してください。
音楽を聴いて、氷が溶けるように気持ちが外にこぼれたら、私たちはお互いにもっとゆったり生きられるような気がします。
ヨーロッパの街角のように、もっと音楽が身近にあったらいいなあというのは、私の昔からの願望なんです。
思わず、うるうる!トイ・ストーリー3
またまた長らくのご無沙汰、失礼しました。今年もあまりブログが更新できないまま、あっという間に12月も半ばになってしまって…。あ~らら~ですね。まったく!
11月はけっこう私自身の研修が続いて、その後、珍しく熱を出して二日ほど寝込みました。ほとんど10年ぶりというくらい珍しいことなのですが…。
そんなこんなですっかり更新が滞っておりました。その間、ブログに書きたいこともチラホラ浮かんではいたのですが、以前よりさらに加速度を増してきた物忘れ度により、書きたかったことはメモする間もなく、思いつくそばから消え去っていったのでした。さて、そんな中でも消えなかった、映画の感想をひとつ。
「トイストーリー3」。夏休みのファミリー・子ども向け映画と思い、期待しないで(失礼?)見たのですが、とんでもない。なかなか見応えがありました。中でも、あるシーンでは胸に迫るものがあって思わず涙…。
すでにご存知だと思いますが、オモチャが主人公の映画です。オモチャの持ち主アンディが大学に入学することになり、オモチャは屋根裏部屋にしまわれることになりました。ところが、ちょっとした手違いが重なって、オモチャ達はゴミ処理工場に送られてしまいます。工場では集められたゴミ(がらくた)と一緒にベルトコンベアーに乗せられ、破砕機めがけて流されていきます。このまま流されて機械に掛かれば粉々です。滝壺に向かう川の流れのごとく、目前に迫る機械に吸い込まれていくがらくたを目にして、オモチャ達はなす術もなく恐怖の声を上げます。
その時、オモチャの一つバズ・ライトイヤー(宇宙戦士のロボット)が一計を案じます。両脇のオモチャに手をさしのべたのです。右のオモチャと手をつなぎ、左側のオモチャと手をつなぐ。そして仲間は次々に隣のオモチャと手をつなぎあい、横一線に並ぶと、みんなの顔から恐怖が消えて、柔らかなほほえみさえも浮かんできます。その間にもベルトコンベアーは容赦なく、オモチャを乗せて破砕機に向かって進んでいくのですが・・・。
ここで、思わず涙腺が緩んでしまったんですよね~、不覚にも。
たとえ状況が好転しなくても、人は恐怖から救われて、笑顔にさえなることができるのだ。人と人とのつながり、心の交流さえあれば、人は不安や恐怖さえも乗り越えることができるのだ。そんなメッセージさえ読み取ってしまったオモチャ物語。なかなかのものでした。
で、この話を20代の人にしたら、「泣く場面が違うでしょ。普通はオモチャとアンディの別れのシーンでしょう」って。レビューを見たら、やはり別れのシーンに感涙というのが多かったです。世代によって違うのかなあ、それとも私が変わってるのかなあ?でもまあ、人それぞれと言うことで…。
「冬のソナタ」と家父長制
「冬のソナタ」といえば、ヨン様ブームを巻き起こした例の韓国ドラマですが、登場人物の中でも、母親ミヒは女性ファンから“悪女”として嫌われている役だそうです。なぜなら、これでもかこれでもかと、次々と悲劇に見舞われるチュンサン(ペ・ヨンジュン)ですが、元はと言えば母親の過去と、その後の誤った判断により起こったことだから、というわけです。
ブームの頃にはほとんど関心がなかったのに、ついに何度目かの再放送の時に、ふと見てしまったのが運のツキ。あまりに都合の良い展開や、すれ違いの連続に、「ありえない」「うっそー!」と思いつつ、毎回ついつい引き込まれて最後まで見てしまった私としては、確かに「悲劇のすべての原因は母親にあり」というのもわからないわけではありませんが…。
そうした“ミヒ=悪女”評に対して、フェミニズムの立場から、別の見方を提示している研究者の意見に出会いました。
未婚の母を選択し、出生の秘密を隠そうとしたために、次々と嘘を重ねなければならなかった母親ミヒ。そのミヒに対して、当時の韓国社会で、あの状況下、男性への愛を貫いて生きていくためには、ミヒにはあの選択しかなかったのではないか、と理解を寄せているのが新鮮でした。
これを読むと、1970~80年代の韓国社会の現状では、ミヒが少しでも自分の納得いく生き方をしたいと望んだとしても、本当に限られた道しか残されていなかったということがわかります。その意味で、ミヒは家父長制の犠牲者と言えるかもしれません。韓国ドラマに出生の秘密に絡んだ同じような筋立てのドラマが多いのも、こうした社会の背景ゆえと考えれば納得できる気がします。
確かに、日本でも1970~80年代といえば、ずいぶん状況は今と違いました。女性は若いうちに結婚して家庭に入るのが当たり前という考え方はまだまだ強かったと思いますし、未婚の母への風当たりも、現在とは比べものにならないくらい強かったように思います。
ですから、儒教の教えの浸透している韓国で、ミヒの置かれた状況が、女性にとっていかに過酷で、ミヒがとった行動以外に選択の余地がほとんどなかったとしても、不思議ではありません。
しかし、というべきか、だからというべきか、現在、韓国は女性支援の対策、特にDV(ドメスティック・バイオレンス)対策では日本よりもずっと充実した政策を推し進めている国になっています。女性の抑圧された現状が厳しかったからこそ、DV対策が待ったなしの緊急性の高い課題にならざるを得なかったのかもしれません。
ミヒやチュンサンのような悲劇をなくすべく、時代は少しずつ変化しています。
それにしても、未だに新しい視点での解釈や話題提供がなされるとは、やっぱり「冬ソナ」、ただのメロドラマではないかも?!
音祭りのわくわく…下地・下舘ライブin原宿
あれよあれよという間に、夏が終わり、気がつくと、季節はすっかり秋の風情。今年の夏は、何となく実感がわかないまま通り過ぎたかのようです。
近所の空き地に柿の木があるのですが、その下を通るたびに柿の実の赤みが増していくのが、季節のモノサシみたいに思って見ています。
というわけで、芸術の秋ですね(食欲の秋とも言いますが、それはまた別の機会に)。
もう5年前になるのですが、セレニティでは「2200kmを結ぶ音祭り!」という音楽イベントを開催しました。→こちら
写真はこちら
そして第二回目を2006年に。2回目の音祭りの写真
その時、イベントの企画から演奏まで終始お手伝いいただいた下館直樹さん(さいたま在住のギタリスト・作曲家)と、その時共演していただいた下地勇さん(宮古島のシンガーソングライター。沖縄から埼玉まで来てくださったことに、まず感謝!)が、東京で再共演することになったそうです。
といっても、もちろんセレニティの企画などではなくて、下地さんの7枚目のレコード発売記念ライブツアーの東京公演になります。
私にとっては、夢の共演なんです。何しろセレニティの活動がご縁で下館さんに出会い、セレニティを通じてお友達になったY子さんに誘われて行った音楽イベントで下地さんの歌を聞き、それが音祭りの開催へとつながったのですから…。
(今、こうして写真を見ると、ホントに多くの方にお世話になったなあと、改めて感謝しています)
最近はバタバタしていてあんまり(というかほとんど)ライブにも行かれないのですが、今度ばかりは行かなくっちゃ!さっそく友人に声を掛け、チケットも入手済み。用意万端で「わたしの秋」を待っているところです。
下館さん、下地さん、それぞれの世界を広げて活躍していらっしゃるのを見聞きするにつれ、「私もがんばらなくっちゃ」と、明るく楽しく励みにさせてもらっています。
11月14日夜、ラフォーレミュージアム原宿ですよ。久しぶりにお二人の生演奏を楽しみにお出かけになりませんか、って何で私が宣伝しているんでしょう。あの音祭りのワクワクを、つい思い出してしまうからなんでしょうね。
やっぱり、変なカウンセリングルームですね。でも、これがセレニティなので、ご容赦下さいませ。
今回のセレニティ通信の表紙に取り上げた言葉、
「The Sence of Wonder」(レイチェル・カーソン)
私は勝手に「わくわく、どきどき」って訳してるんですが、子どもは「わくわく、どきどき」の固まりですね。でも、私たちおとなだって、幾つになっても「わくわく、どきどき」持ち続けましょうね~、皆さん!!
<わくわく、どきどき>の宝物をたくさん、たくさん見つけましょう~♪